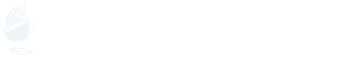男の子の健やかな成長を願う端午の節句。
ゴールディンウィークのこどもの日でもあります。
こどもの日は意味も分かりやすいですが、端午の節句という言葉からは男の子の成長を願う行事は結びつけるのが難しいですね。
端午の節句に限ったことではないですが、伝統行事の意味や由来については知らないことのほうが多いものです。
そこで本日は、そもそも端午の節句とは、どういう意味がある日なのか。
男の子の成長を祝う日になった由来についてお伝えしていきます。
端午の節句の意味は比較的シンプルだったのですが、由来と男の子の節句になった経緯は、日本の歴史の長さを感じるものでしたよ。
端午の節句とは

現在では、端午の節句と言えば、男の子の健やかな成長を願う日で、5月5日の行事。
ですが、端午の節句が男の子の節句となったのは武士が政治を担うようになった鎌倉時代以降のことでした。
もともとの端午の節句とは、
- 奈良時代に中国から伝わった穢れ払いの行事
- 古くから日本の農村で行われてきた田植えの神事
の2つの異なる行事が融合したものでした。
そして端午の節句と聞いて多くの人が思い浮かべる鯉のぼりなども生まれた背景や時代もバラバラで、なかなか歴史を感じる内容なのです。
それぞれ、どの時代から日本で始まったのか、ざっと見るだけでも次のような感じです。
- 粽(ちまき) ⇒ 平安時代
- 鎧兜 ⇒ 鎌倉時代
- 鯉のぼり ⇒ 江戸時代
- 柏餅 ⇒ 江戸時代
また、明治時代にグレゴリオ暦(新暦)が導入されるまでは、太陰太陽暦(旧暦)の5月5日で行われていましたので、時期的には現在の6月の行事でした。
では、端午の節句の意味や由来について順番に詳しく見ていきましょう。
端午の節句の意味
端午の節句が男の子の節句なのに対して、女の子の節句として3月3日の桃の節句があります。
この2つに共通する「節句」という言葉は、
- 季節の変わり目(節)に邪気を祓って
- 無病息災や豊作を願う行事
を意味します。
古くは「節供」と書かれることもあり、季節の変わり目に神様に対して食べ物を供えるという意味もありました。
では、「端午」にはどういう意味があるのでしょうか。
端午の意味するところ
- 端 ⇒ 初め
- 午 ⇒ 午の日
つまり、端午とは月初めの午の日を意味しています。
でも先ほどお伝えしたとおり、端午の節句は5月5日と決まった日付です。
旧暦にせよ新暦にせよ、5月5日が午の日になるとは限りませんよね。
節句という考えは中国から伝わったもので、端午の節句もその起源は中国にあります。
「午」は、中国語で”うー”と発音されます。
そして、同じく”うー”と発音するのが「五」。(日本語でも両方とも”ご”ですが(笑))

さらに、旧暦の5月は午の月。
また、昔の中国では奇数の重なる月日を特別な日と考えていましたので、午の月(5月)の五の日が、端午の節句の日として邪気を祓う行事の日となったのでした。
ただ5月5日は、中国では良い意味で特別な日ではなかったようなのです。続いて詳しくお伝えしていきますね。
端午の節句の2つの由来

さて、ここでは最初にお伝えした本来の2つの端午の節句の由来、
- 奈良時代に中国から伝わった穢れ払いの行事
- 古くから日本の農村で行われてきた田植えの神事
について一緒に見ていきましょう。(端午の節句がなぜ男の子の成長を祝う日になったかは、この後歴史の流れに沿って見ていきますよ~)
起源は中国の穢れ払いの行事
端午の節句となった5月5日は、中国では大変縁起の悪い厄日とされていました。
中国で生まれた陰陽五行の思想では、午の月(5月)は凶の月として、「悪月」という異名をとるほど忌み慎む月。
そして、発音が「午」に通じる5日は5月(午の月)の中で最も縁起が悪いと考えられていたのです。
実際、旧暦の5月には戦乱や天災が多く起こっていたことも5月5日を凶日とする裏付けになったのです。(偶然だとは思うのですが・・・)
怖い話になってしまいますが、5月5日に生まれた子供は、親を殺すような害のある存在になると信じられていて、5月5日に子供が生まれると捨てるという風習まであったのです。
そんな厄日と信じられてきた5月5日の端午の日に邪気を祓う厄払いの行事が行われるようになったのは説得力がありますよね。
6世紀の中国の風習や年中行事を記録した「荊楚歳時記(けいそさいじき)」によると、当時、すでに端午の節句には次のような行事があったと残されています。
- 菖蒲などの薬湯に入る
- 菖蒲やヨモギなど野草を摘む
- 菖蒲やヨモギで作った人形や虎を門や軒下に飾る
- 菖蒲の根を刻んで入れた菖蒲酒を飲む

端午の節句は、またの名を菖蒲の節句とも言いますが、菖蒲のような香りの高い草には邪気を祓う力があると信じられていたことから来ています。
端午の節句が宮中行事に
やがて端午の節句が日本に伝わると、宮中の年中行事として取り入れられるようになります。
日本における端午の節句の最も古い記録は、日本書紀に残された611年(推古19年)の薬猟の行事です。
ここでいう薬は鹿の若角のこと。
当時の端午の節句では、
- 男性が鹿を狩り
- 女性は野原で薬草を摘む
ということが恒例でした。
やがて薬猟が行われなくなり、代わりとなったのが騎射や走馬といった儀式など。
現在も5月5日に神社で見られる流鏑馬(やぶさめ)の起源とされています。
他には、宮中では邪気を祓う菖蒲で宮中の建物の屋根を葺いたり、菖蒲湯に入ったり菖蒲酒を飲んだりということも行われていました。
また、公式行事として開かれる「端午の節会(せちえ)」では、菖蒲で作った菖蒲蔓(かずら)を冠につけて参列し、天皇から薬玉(薬草を丸く固めて飾りをつけたもの)を賜わる決まりでした。

日本古来の田植えの神事と融合
さて、中国からの端午の節句が宮中で行事として取り入れられた一方、日本には古くから田植えが始まる旧暦5月に農村で行われてきた神事がありました。
お米が豊作になるかどうかは、農村にとっては死活問題。
そんな重要な田植えを始める5月は、日本においても物忌み月とされて、”慎むべき月”でした。
決して縁起の良くない5月の厄災が稲作に及ぶのを祓い、豊作を祈願するために行われていたのが「皐月忌み(さつきいみ)」と呼ばれる田植えの神事です。
皐月忌みの神事の主役となるのは、早乙女(さおとめ)と呼ばれるうら若き乙女たち。
田植えは生命を生み出す女性の役割と考えられていたためです。
中国では、端午の節句は厄災や穢れを祓うものでしたが、日本の田植え神事「皐月忌み」は豊作を願うために穢れを祓う儀式だったわけです。

そして、この日本の端午の節句の行事になったのだと言われています。
中国から伝わった端午の節句は、最初は宮中で行われ、やがて武家に、そして庶民へと広がっていきます。
背景に、皐月忌みの神事があったから、定着しやすかったのかもしれませんね。
では続いて、端午の節句が、男子の健やかな成長を願う行事に変わっていった経緯を見ていくことにしましょう。
端午の節句が男の子の節句になるまで
中国から伝わった当初は、厄災を祓う清めの行事という性格が強かった端午の節句ですが、鎌倉時代に入ると男子の成長を祝い健康を祈る行事へと姿を変えていきます。
鎌倉時代、武家の間で男子の成長を願う行事へ
端午の節句で穢れを祓うために用いられてきたのが、香りが高く魔を祓う力があると信じられてきた菖蒲です。
平安時代の後期から力を持つようになった武士ですが、鎌倉幕府が開かれ、本格的な武士の時代が始まります。
武士の家で大切なスキルと言えば、言うまでもなく剣や弓と言った武術。
- 武を重んじることを表す「尚武」が、端午の節句で厄災を祓う「菖蒲」と同じ”しょうぶ”と読むこと
- 菖蒲の葉が、刀の形に似ていること
から、武家を中心に端午の節句が男子の成長を祝い健康を願う行事と性質を変えて行きました。
のちに江戸幕府が端午の節句を五節句の一つに定めます。
ですが、すでに鎌倉幕府、室町幕府でも端午の節句を祝日と扱っていました。
また、この頃から鎧や兜を室内に飾る風習も生まれたと伝わります。
武士にとって、鎧や兜は身体を守ってくれる大切な武具です。
武運を願って、鎧や兜を神社に奉納する習わしから、成長する我が子の身の安全を祈って飾られるようになったのでしょう。

江戸時代、広く庶民も男子の成長を祝うように
江戸時代に入ると、端午の節句は五節句の一つに定められ江戸幕府の重要な年中行事となります。
また260年に及ぶ泰平の世が続いた江戸時代は、庶民文化が花開いた時代でもあります。
豊かになった庶民の間でも武家をまねて端午の節句が祝われるようになりました。
工芸技術の発達に伴って、鎧・兜や武者人形などの飾り物もどんどん精巧で華やかなものになったのです。
そして、江戸時代に誕生したものが、鯉のぼりと柏餅です。
- 鯉のぼりは、滝を上った鯉が竜になったという中国の龍門伝説から、我が子の立身出世を願うものとして
- 柏餅は、柏が夏に新しい葉が出るまで古い葉を落とさないことから、家系が絶えない縁起物として
端午の節句に欠かせないものとなりました。
柏餅と粽(ちまき)
柏餅は、日本生まれで江戸時代から端午の節句の和菓子となりましたが、粽は平安時代に中国から伝わった食べ物です。
しかも、粽が端午の節句の食べ物となった由来は、一説には紀元前の中国の故事によると言われています。
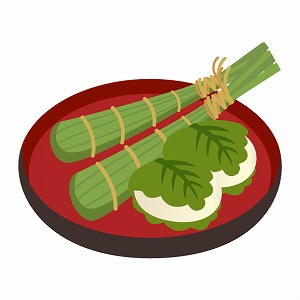
紀元前、中国にあった楚の国に屈原という人物がいました。
屈原は詩人としても有名ですが、同時に人望の厚い政治家でもあったのですが、政争に敗れて失脚してしまいます。
その後、楚の国の行く末を憂いた屈原は、5月5日に川に身を投げて死んでしまうのです。
屈原の死を嘆いた人々が、屈原の慰霊と屈原の死体が川の魚の餌とならないよう、餅を川に投げ入れるようになります。
この風習がやがて、国の安泰を祈願する風習として中国前後に広まったのでした。
一方で、粽は屈原以前から端午の節句や夏至に食べていたという古い記録があるとして屈原の故事と端午の節句の粽は無関係という考えもあるようです。
いずれにせよ、粽は端午の節句より少し遅れて日本に伝わり、西日本を中心に端午の節句の和菓子として定着したのでした。
富国強兵の明治を経て戦後は国民の祝日に
明治に入り、西洋文明がもてはやされるようになると端午の節句のような伝統行事に否定的な意見が政府の間で見られた時期がありました。
ですが、強い男子に育ってほしいという親の願いと、富国強兵という国の方針が一致。
鯉のぼりや武者人形の端午の節句飾りは庶民の間でさらに広く普及するようになりました。
そして、第二次世界大戦後の祝日法の改正により、端午の節句はこどもの日の祝日に制定。
現在も男の子の成長を祝う日として、初めての節句を親戚がそろって祝う習慣が続いています。

まとめ
5月5日の端午の節句は、男の子の健やかな成長を願う日です。
端午の節句とは
- 奈良時代に中国から伝わった穢れ払いの行事
- 古くから日本の農村で行われてきた田植えの神事
の2つの異なる行事に由来します。
端午は、月の初め(端)の午の日という意味です。
午と五が中国では「うー」と発音が同じであることと、旧暦5月が午の月であることから、端午の節句は5月5日の行事となりました。
そして、中国では午の月(5月)は凶の月であり、うー(午=五)が重なる5月5日は最悪の厄日とされていました。
厄日である5月5日の厄災祓いのために、端午の節句には香りに魔を祓う力があると信じられていた菖蒲を用いた厄払いの風習が行われました。
一方、日本でも5月は物忌み月。
物事を慎むべき月とされましたが、ちょうど田植えを始める時期です。
5月の厄災が稲作に及ぶのを祓い、田の神に豊作を祈願するために、田植えを行う早乙女ちが菖蒲やヨモギで屋根を葺いた小屋にこもり身を清める皐月忌みの神事が行われていました。
この2つの異なる風習が融合し日本の端午の節句の行事になったのだと言われています。
やがて、中国から伝わった当初は、厄災を祓う清めの行事という性格が強かった端午の節句ですが、鎌倉時代に入ると男子の成長を祝い健康を祈る行事へと姿を変えていきます。
- 武を重んじることを表す「尚武」が、端午の節句で厄災を祓う「菖蒲」と同じ”しょうぶ”と読むこと
- 菖蒲の葉が、刀の形に似ていること
から、武家を中心に端午の節句が男子の成長を祝い健康を願う行事と変わっていきました。
江戸時代に入ると、端午の節句は庶民の間にも広がっていきます。現在では端午の節句に付き物の鯉のぼりや柏餅は、江戸時代に誕生したものです。
明治に入り、強い男子に育ってほしいという親の願いと、富国強兵という国の方針が一致。
鯉のぼりや武者人形の端午の節句飾りは、庶民の間でさらに広く普及するようになりました。
そして、第二次世界大戦後の祝日法の改正により、端午の節句はこどもの日の祝日に制定。
現在も男の子の成長を祝う日として、初めての節句を親戚がそろって祝う習慣が続いています。