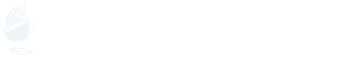数字が使われていることわざは多いですが、いざとなるとなかなか思い浮かばないものですよね。
ことわざの先頭に入っているとまだましなのですが、途中に入っているものだと、さらに思い浮かびません。
また、一や三、千が入っていることわざも比較的思い出しやすいですが、四・六あたりはうんうん唸るだけでなかなか出てきません(笑)。
本日は、そんな数字が入ったことわざを150個を集めてきました!意味と共にまとめていますので、ゆっくりご覧ください~。
(ちなみに数字が2種類以上入っている場合は、最初の数字で分類しています。)
「一」から「九」までが入ったことわざ
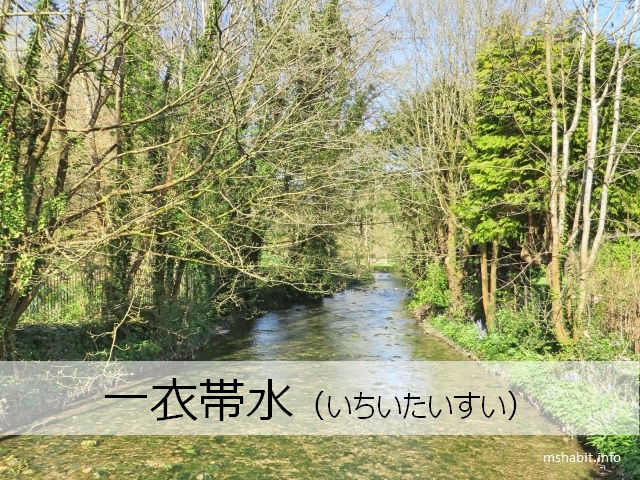
「一」が入ったことわざ
一衣帯水(いちいたいすい)
- 一筋の帯のように狭い川や海峡
- 狭い隔たりがあるだけで、とても近くにあることのたとえ
一か八か(いちかばちか)
- うまくいくかどうか分からないが、運を天に任せて思い切ってやってみる様子
「一」は丁、「八」は半という江戸時代の賭博用語が由来です。
一議に及ばず(いちぎにおよばず)
- あれこれ議論する必要はない
一期一会(いちごいちえ)
- 一生に一度の出会いのこと
茶道に由来する言葉です。
再び会えると思わずに、その時の出会いを大切にすべきという戒めです。

一事が万事(いちじがばんじ)
- ある一つの物事に対する姿勢を見れば、他のすべての面についてもどういう姿勢が推測できる
人の嫌な行動を非難するときに使うことが多いでしょうか。
「一事が万事」が正解な時もあれば、外れることもあり。人は、簡単には分かりません(笑)。
一日三秋(いちじつさんしゅう)
- 一日会わないだけでも3年も会わないように長く感じるという意味で、早く会いたいという気持ちを表す言葉
一日の長(いちじつのちょう)
- 一日早く生まれたという意味で、わずかでも年齢が上であること
- 知識や技能、経験が、他の人より少しだけ優れていること
「論語」から来ています。
一日の計は朝にあり(いちじつのけいはあしたにあり)
- 物事は、最初に計画をしっかりと立ててから取り掛かるべきものだという例え
「一年の計は元旦にあり」と同じ意味ですね。
一樹の陰も他生の縁(いちじゅのかげもたしょうのえん)
- 人は誰でも互いに親しみあい親切にすべきという仏教の教えをあらわした言葉
見知らぬ人同士が同じ木の陰に休むのも前世からの因縁であるという意味です。
「袖振り合うも他生の縁」と同じ意味です。
一場の春夢(いちじょうのしゅんむ)
- 春の夢のように、きわめてはかないことのたとえ
「一場」は、”その場だけ”という意味です。
人生の栄華のはかなさを表しています。
「侯鯖録」が出典です。
一難去ってまた一難(いちなんさってまたいちなん)
- 災難や面倒なことが次から次にやってくること
一つ解決したとホッとするのもつかの間、次のトラブルが起こる。そんな時が確かにあります。
じたばたしても仕方ないので、一つずつこなすしか無いのですけどね。
こういう事は多いと見え、「前門の虎後門の狼」「泣きっ面に蜂」「弱り目に祟り目」と、同じ意味のことわざが多いですね。
一に看病二に薬(いちにかんびょうににくすり)
- 病気を治すために最も必要なのは手厚い看護で、薬はその次である
一念天に通ず(いちねんてんにつうず)
- 必ずやり通すという強い決意があれば、その心が天に通じ必ずかなうものだ
同じ意味のことわざに「石に立つ矢」、「思う念力岩をも通す」「精神一到何事か成らざらん」があります。
一引き二才三学問(いちひきにさいさんがくもん)
- 出世には、第一に上の人からの引き立てが必要であり、第二に本人の才能、第三に学問である
一姫二太郎(いちひめにたろう)
- 最初の子は女の子、次の子は男の子という順番が育てやすい
- 子供の数は、男の子2人・女の子1人が、理想だ
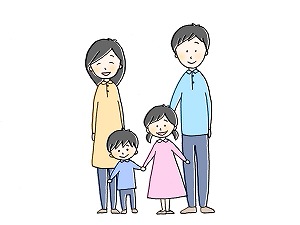
一富士二鷹三茄子(いちふじにたかさんなすび)
- 初夢で見ると縁起が良いとされるものを順番に並べた語
徳川家康が基礎を築いた駿河(現在の静岡県)の名物と言われていますね。
一文惜しみの百知らず(いちもんおしみのひゃくしらず)
- わずかな金額を出し惜しんだがために、将来の利益を失うこと
一葉落ちて天下の秋を知る(いちようおちててんかのあきをしる)
- 小さな前兆から、将来の成り行きや衰退など良くないことを察知すること
落葉の早い青桐の葉が1枚落ちるのを見て、秋の気配を知るという意味です。
一陽来復(いちようらいふく)
- 冬至で冬の寒さがピークに達し、続いて春の暖かさが訪れること
- 悪いことが続いた後に、物事がようやく幸運に向かうこと
一蓮托生(いちれんたくしょう)
- 結果はどうあろうと、行動や運命をともにすること(多くは悪いことを一緒にすること)
仏教用語が元です。
死後に、同じ蓮華の上に生まれ変わるという教えを表しています。
一を聞いて十を知る(いちをきいてじゅうをしる)
- わずかな事を聞くだけで多くのことを理解できるほど、優秀であること
一気呵成(いっきかせい)
- 一気に物事を最後まで仕上げること
「呵」は、筆に息を吹きかけることです。
文章などを一気に書き上げるというのが本来の意味です。
一騎当千(いっきとうせん)
- 一人の騎兵で千人の敵を相手に出来るほど強いという意味で、人並外れた才能や経験があること
「史記・項羽紀」が出典です。
一挙手一投足(いっきょしゅいっとうそく)
- 一つ一つの細かな動きや行動
- わずかな努力や骨折り
一回手を上げ、一回足を踏み出すという意味です。
一挙両得(いっきょりょうとく)
- 一つの事をすることによって、二つの利益を同時に得ること
「一石二鳥」と同じ意味です。
一矢を報いる(いっしをむくいる)
- 大勢を変えるには及ばなくても、わずかであっても反撃・仕返しをする
元の意味は、敵の攻撃に対して矢を射返すというものですが、それが転じて今の意味になりました。
一寸先は闇(いっすんさきはやみ)
- 先のことは、どんなに近い将来でも何が起こるか分からない
いろはかるた(京都)の1枚だったものです。一寸は約3㎝という単位。そんなわずか先であっても、どんな不幸が待ち受けているか分からないという例えです。
一寸の光陰軽んずべからず(いっすんのこういんかろんずべからず)
- わずかな時間であっても無駄に過ごしてはいけない
「光陰」は時間を意味する言葉です。
原文は、偶成という詩ですが、前の区にあたる『少年老い易く学成り難し』も有名ですね。
一寸の虫にも五分の魂(いっすんのむしにもごぶのたましい)
- どんなに小さく弱い者にも、相応の意地があるものだから、侮ってはいけない
一石二鳥(いっせきにちょう)
- 一つの事をすることによって、二つの利益や成果を得ること
一つの石を投げて、二羽の鳥を打ち落とすという意味です。
「一挙両得」と同じ意味です。
一銭を笑う者は一銭に泣く(いっせんをうしなうものはいっせんになく)
- わずかな金額を軽んずる者は、わずかな金額の不足に困ることになるという意味で、わずかな金額でも大事にするようにという戒め
最近は、「一円を笑うものは一円に泣く」と言いますね。

一朝一夕(いっちょういっせき)
- 一日か二日という意味で、わずかな時間や短時間をあらわす
一敗地に塗れる(いっぱいちにまみれる)
- 大敗し、再起不能なまでの打撃を受けること
戦場で、死者の内臓が散らばって泥にまみれるという意味です。
「史記・高祖紀」が出典です。
起きて半畳寝て一畳(おきてはんじょうねていちじょう)
- 人間が生きていくのに、それほど多くの物は必要ない
「起きて半畳寝て一畳、天下取っても二合半」と続けて使うことも。
寝起きするには、一畳もあれば十分な広さ。天下を取ったとしても、一食に二合のご飯は要らない。と人間の贅沢を求める心を戒めることわざです。
親子は一世夫婦は二世主従は三世(おやこはいっせふうふはにせしゅじゅうはさんぜ)
- 親子の関係は現世だけであり、夫婦の関係は二世(前世と現世、もしくは現世と来世)にわたるが、主従の関係は、前世・現世・来世にわたるほど深い因縁があるものだ
仏教の教えに基づく言葉です。
封建時代ならではの主従という人間関係に一番の重きを置いた言葉ですね。
鎧袖一触(がいしゅういっしょく)
- 鎧(よろい)の袖にちょっと触れたぐらいで、相手を簡単に打ち負かすこと
⇒かっこいいことわざと四字熟語!スポーツなど目的に応じて使える100選!
聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥(きくはいっしょうのはじ きかぬはいっしょうのはじ)
- 知らないことを人に聞くのは、その時は恥ずかしいことかもしれないが、聞かずに知らないままでいると、かえって恥をかくことになるから、知らないことは知っている人にその場で聞くのが良い
桐一葉(きりひとは)
- 桐の葉の落葉は、形成の逆転や衰亡の兆しを暗示しているとしていう言葉
「一葉落ちて天下の秋を知る」と似たことわざです。
こちらは、衰亡の兆しを感じるというより、その象徴ととらえます。
軌を一にする(きをいつにする)
- 行き方や物事のやり方が同じであること
「軌」は、車の両輪の間隔です。
どの車も両輪の幅を同じにするというのが元の意味です。
鶏群の一鶴(けいぐんのいっかく)
- 多くの凡人の中に、一人だけ突出して優れた人物がいることのたとえ
乾坤一擲(けんこんいってき)
- 運命をかけて思い切った大勝負をすること
「乾坤」とは、天地のことです。
天地をかけた大勝負というのが本来の意味です。
紅一点(こういってん)
- 男性の中に女性が一人いること
王安石の詩の一節です。
”万緑叢中紅一点(ばんりょくそうちゅうこういってん)、
人を動かすの春色多きを須(もち)いず”
小姑一人は鬼千匹に当たる(こじゅうとひとりはおにせんびきにあたる)
- 嫁の立場からは、夫の兄弟姉妹は、一人が鬼1000匹に思えるほど、面倒で苦労の種だということ
地獄は壁一重(じごくはかべひとえ)
- 正しい道を一歩踏み間違えただけで、たちまち罪を犯してしまうというたとえ
春宵一刻値千金(しゅんしょういっこくあたいせんきん)
- 春の夜はとても趣が深く、短い時間であっても千金に値するほど心地が良いものだ
「花に清香有り月に陰有り」と続く蘇軾の詩「春秋」の一節です。
正直は一生の宝(しょうじきはいっしょうのたから)
- 正直さは、信頼と幸福をもたらすから、一生通して守るべき宝である
精神一到何事か成らざらん(せいしんいっとうなにごとかならざらん)
- 精神を集中して努力すれば、どんな困難なことでも出来ないことは無い
備わるを一人に求むるなかれ(そなわるをいちにんにもとむるなかれ)
- 一人の人間に、完全であることを求めてはいけない
「論語」の一節です。
大山鳴動して鼠一匹(たいざんめいどうしてねずみいっぴき)
- 大変なことが起こると大騒ぎした割には、大した結果にならなかったこと

頂門一針(ちょうもんいっしん)
- 人の急所を突く鋭い忠告や戒め
鶴の一声(つるのひとこえ)
- その場にいる多くの人を従わせる権威や権力のある人の一言
習うは一生(ならうはいっしょう)
- 何歳になっても学ぶべきことがあり、一生が勉強である
娘一人に婿八人(むすめひとりにむこはちにん)
- 一人の娘に婿候補が大勢いること
- 一つの物事について、希望者が非常に多いことのたとえ
ローマは一日にして成らず(ろーまはいちにちにしてならず)
- 大事業の完成には、長い年月と努力が必要となる
”Rome was not built in a day.”を訳したものです。
「二」が入ったことわざ
心は二つ身は一つ(こころはふたつみはひとつ)
- 一度に多くのことを望んでも、自分の体は一つしかないため思うようにはいかないこと
同じ意味に「二兎を追う者は一兎をも得ず」があります。
習慣は第二の天性なり(しゅうかんはだいにのてんせいなり)
- 習慣は、生まれ持った性質と同じぐらいに、その人の生活や行動に影響する
”Custom is a second nature.”が原文です。
天は二物を与えず(てんはにぶつをあたえず)
- 天は一人の人に長所や美点をいくつも与えはしないのだから、長所ばかりの人はいないということ
二階から目薬(にかいからめぐすり)
- 二階から階下の人に目薬をさすように、もどかしく思うような効果が無いこと
「天井から目薬」とも言います。いろはかるた(京都)の1枚です。
二足の草鞋を履く(にそくのわらじをはく)
- 普通なら両立しないような2つの職業を同じ人が兼ねること
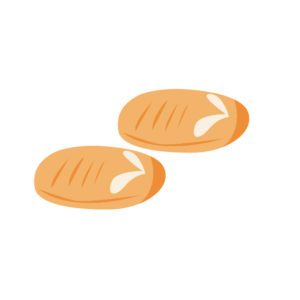
江戸時代、ばくち打ちでありながら、罪人を捕まえる役人(捕吏)を兼ねる人がいたそうです。それって本当に両立できたんでしょうか??
二度あることは三度ある(にどあることはさんどある)
- 同じことが二度起これば、もう一度同じことが起こることが多いものだ
物事は繰り返されるから、気を付けるようにという戒めも込められています。
二兎を追う者は一兎をも得ず(にとをおうものはいっとをもえず)
- 同時に二つのことを得ようと欲張っても、どちらもうまく行かないものだ
二匹のウサギをおいかけても一匹も捕まえられないという意味ですね。
なんとローマの古いことわざが元でした。
二の足を踏む(にのあしをふむ)
- 先に進めず足踏みをするという意味で、決断をためらう様子のこと
二の句が継げない(にのくがつげない)
- 相手の言葉にあきれたり気後れしたりして、次に言うべき言葉が出てこないこと
二の舞を演じる(にのまいをふむ)
- 前の人がやった失敗を同じように繰り返すこと
「安摩(あま)」という舞楽の中で、それをまねて滑稽に見せる舞を「二の舞」と読んだことから出来たことわざです。
人を呪わば穴二つ(ひとをのろわばあなふたつ)
- 人に危害を与えようとすれば、自分にもその報いが来るということ
人を呪って穴を掘るときは、自分を埋める穴も用意する必要があるという、とても怖い意味のことわざです。
武士に二言はない(ぶしににごんはない)
- 武士は一度口にしたことは必ず守りとおすという意味
武士という身分が何よりも信義を重んじだという事を表しています。
「三」が入ったことわざ
石の上にも三年(いしのうえにもさんねん)
- どんなことでも、辛抱して続ければいつかは成功する
冷たい石の上でも3年座っていれば暖かくなるというのが素の意味です。3年というのは、続けるという辛抱の期間の比喩ですが、3年続けるというのは確かに一つの目安だと感じます。
犬は三日飼えば三年恩を忘れぬ(いぬはみっかかえばさんねんおんをわすれぬ)
- 犬でもそれだけ恩を忘れないのだから、人はなおさら恩を忘れてはいけない
「後足で砂をかける」と同じく、恩を大切にしなさいという戒めのことわざですが、犬に負けるなと言われると辛いものがあります(笑)。
女三人寄れば姦しい(おんなさんにんよればかしましい)
- 女性は、おしゃべりだから、3人集まると大変やかましい
女が3つ合わせて「姦しい(かしましい)」と読むことから出来たことわざです。
悔しいですが、反論できません(笑)。

女は三界に家無し(おんなはさんがいにいえなし)
- 女性は若い時は父親に従い、結婚すれば夫に従い、年老いてからは子に従うものだから、一生の間安住できる場所を持たない
昔の話ですね!(一蹴)
子は三界の首枷(こはさんがいのくびっかせ)
- 親は子どもを思う心に縛られて生きていくものだということ
いろはがるた(江戸)の1枚。
「首枷」は、罪人の首にはめて体の自由を拘束する道具のことです。
三顧の礼(さんこのれい)
- 目上の人が、自分より格下ながら優れた人に対して、礼を尽くして仕事などをたのむこと
三歳の翁百歳の童子(さんさいのおきな ひゃくさいのどうじ)
- 3歳のような幼子でも分別のある人がいる一方で、年をとっても分別のない愚かな人がいるものだ
三尺下がって師の影を踏まず(さんじゃくさがってしのかげをふまず)
- 師に対しては、尊敬の念をもって礼儀を失わないよう説いた言葉
仏教の作法から基づきます。
師である僧に随行するときは、三尺下がって陰も踏んではいけないとされていました。
三十六計逃げるに如かず(さんじゅうろっけいにげるにしかず)
- 分が悪いと思ったら、逃げ出すのが一番良いということ
三寸の舌に五尺の身を亡ぼす(さんずんのしたにごしゃくのみをほろぼす)
- 不用意な発言をしたばかりに、災いを招いてしまい身を滅ぼすことがあるので、口を慎むよう戒める言葉
三度の飯より好き(さんどのめしよりすき)
- 一日の三食がどうでもよくなるほど、あることが好きで熱中していることのたとえ
三度目の正直(さんどめのしょうじき)
- 何かをするときに、初めは失敗しても、3回目ぐらいにはうまくできるようになるものだ
三人寄れば文殊の知恵(さんにんよればもんじゅのちえ)
- 1人では無理でも、3人集まって考えれば、凡人でも優れた知恵が出てくるものだ
「文殊」は、知恵の徳を持つと言われる菩薩様です。
三年飛ばず鳴かず(さんねんとばずなかず)
- 活躍できる機会が来るのをじっと待つこと
「史記・楚世家」の故事に基づきます。
”三年間飛びも鳴きもしないが、飛べば天高く上がり、鳴けば人を驚かすだろう”という意味です。
三拍子そろう(さんびょうしそろう)
- 必要な条件や要素をすべて備えていること
小鼓、大鼓、笛で拍子をとることから生まれたことわざです。
三遍回って煙草にしょ(さんべんまわってたばこにしょ)
- 仕事にかかるときは、年を入れて手落ちが無いようによく確認するようにという戒め
いろはがるた(江戸)の1枚です。
夜回りで、三度見回って異常が無いことを確認してから、ようやく休憩するという意味です。
三面六臂(さんめんろっぴ)
- 顔が3つで腕が6本という仏像の姿から、一人で何人分もの働きをすること
朝三暮四(ちょうさんぼし)
- 人を口先でうまくだますこと
- 目先の利益にとらわれて、本質に気づかないこと
宋の狙公が、猿に「朝に三つ、夕方に4つトチの実をやる」と言ったところ、猿が怒ったので、「朝に四つ、夕方に三つ」と言ったところ喜んだという故事に基づきます。
盗人にも三分の理(ぬすっとにもさんぶのり)
- 悪事を働く人間にも、悪事を正当化するそれなりの理屈があるという意味で、どんなことにも理屈はつけられるということ
「泥棒にも三分の理」とも言います。
早起きは三文の得(はやおきはさんもんのとく)
- 早起きをすると、必ず何か得をするということ
朝寝坊をいましめる言葉です。

仏の顔も三度(ほとけのかおもさんど)
- どんなに穏やかな人であっても、ひどい仕打ちを繰り返されれば腹を立てるということ
いろはがるた(京都)の1枚です。
「地蔵の顔も三度」とも言います。
同じ意味に「兎も七日なぶれば噛みつく」というものもあります。
三日天下(みっかてんか)
- ごく短い間、権力や地位を得ること
明智光秀が織田信長を倒して天下を取ったが、わずか12日で豊臣秀吉に滅ぼされたことに基づきます。
三日坊主(みっかぼうず)
- 飽きやすく、一つのことを続けられない人のこと
出家したものの、修行と戒律の厳しさから、3日で還俗してしまうことを意味します。
三つ子の魂百まで(みつごのたましいひゃくまで)
- 幼いころの性格や気質は、一生変わらないものだ
「三つ子」は、三歳の子どもの事ですね。
孟母三遷の教え(もうぼさんせんのおしえ)
- 子どもの教育に良い環境を選ぶこと
孟子の母が、孟子のために3回引っ越したという逸話から出来た言葉です。
初めは墓地の近く⇒葬式ごっこをした
次は市場の近く⇒商売の真似をして遊んだ
最後に学校の近く⇒先生ごっこをした
これで、ようやく孟子のお母さんは安心して引っ越すのを止めたのだそうです。
桃栗三年柿八年(ももくりさんねんかきはちねん)
- 植えてから実がなるまで、桃・栗は3年、柿は8年かかるように、物事を成し遂げるには相応の時間がかかるということ
「四」が入ったことわざ
四海兄弟(しかいけいてい)
- 全ての人々は、みなが兄弟のように仲良く愛し合うべきだということ
「論語・顔淵」の一節からきています。
四角四面(しかくしめん)
- 生真面目で、堅苦しい考え方しかできずに、融通の利かないことのたとえ
四苦八苦(しくはっく)
- ありとあらゆる苦しみ
- 耐えがたい非常な苦しみ
「八苦」とは、仏教で人間の苦しみを分類したものです。
生老病死という四苦に、愛別離苦(あいべつりく・怨憎会(おんぞうえ)苦・求不得(ぐふとく)苦・五陰盛(ごおんじょう)苦の四苦を指します。
四知(しち)
- 2人だけの秘密であっても、天と地も知っているので四者が知っているという意味で、秘密は他に漏れる物であるということ
「天知る神知る我知る子(し)知る」が同じ意味です。
四百四病の外(しひゃくしびょうのほか)
- 恋の病のこと
「四百四病」は、人がかかる全ての病気のことですが、恋の病は「四百四病」に入らないんですね。

四面楚歌(しめんそか)
- 周囲は敵や反対する人ばかりで、助けてくれる人もなく孤立した状態のこと
「史記・項羽紀」が出典です。
「五」が入ったことわざ
堪忍五両(かんにんごりょう)
- 腹が立っても、じっと堪えていれば、それが大きな得となる
五十歩百歩(ごじっぽひゃっぽ)
- どちらも似たりよったりで、大したちがいがない
戦場で50歩退却した者が100歩退却した者を臆病だと笑ったが、逃げたという点では両者に差はないという「孟子」の寓話から出来たことわざです。
五十にして天命を知る(ごじゅうにしててんめいをしる)
- 人間は50歳になってようやく自分の人生の運命や宿命が分かる
「論語」の有名な一節ですね。
五風十雨(ごふうじゅうう)
- 5日ごとに風が吹き、10日ごとに雨が降るという意味で、天候が順調なこと、特に農業に最適な気候のこと
五里霧中(ごりむちゅう)
- 深い霧の中にいるように、方針を見失い判断ができずに、どうしていいか迷うこと
「後漢書・張楷伝」の故事に基づきます。
「六」が入ったことわざ
六日の菖蒲 十日の菊(むいかのしょうぶ とおかのきく)
- 時機が遅れて役に立たないこと
- 肝心のときに間に合わなくては意味が無いこと
菖蒲は5月5日の端午の節句に、菊は9月9日の重陽の節句で飾る花です。
それが一日遅れで間に合っていないということですね。
六十の手習い(ろくじゅうのてならい)
- 六十になってから文字を習い始めるという意味で、年を取ってから学問や習い事を始めること
「七」が入ったことわざ
伊勢へ七度 熊野へ三度(いせへななたび くまのへさんど)
- あちこちの寺社に何度もお参りするという意味で、信心が厚いことのたとえ
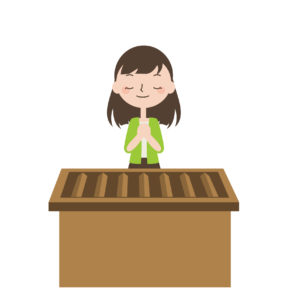
色の白いは七難隠す(いろのしろいはしちなんかくす)
- 女性は色白であれば、顔や形が少々悪くても、欠点をカバーして美しく見えるものだ
私も色白の方なので良く母から言われましたが、言われた方は複雑な気持ちになる言葉です(笑)。
親の七光り(おやのななひかり)
- 親の威光のおかげで、子どもにはそれほど実力が無いのに世間で重んじられること
敷居を跨げば七人の滴あり(しきいをまたげばしちにんのてきあり)
- 一歩家の外から社会に出て活動するときには、多くの競争相手や敵がいるものだ
「男は」を付けて言われてきましたが、最近は男女両方に言えるとして省くようになりました。
七転八倒(しちてんばっとう)
- 激しい苦痛のために、のたうち回ること
- ひどく混乱している様子
なくて七癖(なくてななくせ)
- 人は誰でも多かれ少なかれ、何らかの癖を持っているものだ
七転び八起き(ななころびやおき)
- 何度失敗してもくじけず、そのつど奮起してさらに努力すれば、最後に成功するということ
七回転んでも八回立ち上がるという意味です。
七度尋ねて人をうたがえ(ななどたずねてひとをうたがえ)
- 物を失くしたときは何度も探してから、人に訊ねるべきで、軽々しく人を疑ってはいけない
人の噂も七十五日(ひとのうわさもしちじゅうごにち)
- 世間というのは忘れやすいものだから、どんな噂であってもいつまでも続かないということ
「急ぐべからず、不自由を常と思えば不足なし」と続きます。
「八」が入ったことわざ
当たるも八卦当たらぬも八卦(あたるもはっけあたらぬもはっけ)
- 占いは当たることもあれば外れることもあるものなので、結果を気にする必要はない
結果を気にせず、まずはトライ!という意味にも使いますよ。
嘘八百を並べる(うそはっぴゃくをならべる)
- 話の辻褄を合わせようと、次から次に出鱈目や嘘をつき続けること
口八丁手八丁(くちはっちょうてはっちょう)
- 言うこと、すること、達者でぬかりがない様子
八方美人(はっぽうびじん)
- 誰からもよく思われようと、相手に合わせて自分の意見や態度を変える振る舞いや人のこと
元々は、非の打ちどころがない美人という意味でした。
腹八分目に医者いらず(はらはちぶんめにいしゃいらず)
- 食事を腹八分目ぐらいにしておくと、健康でいられるので、医者にかからないで済む
「腹も身の内」「節制は最良の薬なり」が同じような意味です。

「九」が入ったことわざ
九牛の一毛(きゅうぎゅうのいちもう)
- きわめて多くの中のわずかな部分であり取るに足らない小さなこと
漢書の司馬遷伝の故事に基づくことわざです。
九死に一生を得る(きゅうしにいっしょうをえる)
- 普通に考えれば命を失うような危ない状態から、かろうじて助かること
「十」、「百」、「千」、「万」が入ったことわざ

「十」が入ったことわざ
十把一絡げ(じっぱひとからげ)
- 良い悪いの区別もなく、全部を一まとめにして扱うこと
- 取り上げる価値が無いものとして雑に扱うこと
十で神童十五で才子二十すぎれば只の人(とおでしんどうじゅうごでさいしはたちすぎればただのひと)
- 小さい時は神童と呼ばれるほど優れているようでも、大人になると結局は普通に人になる
「百」が入ったことわざ
明日の百より今日の五十(あすのひゃくよりきょうのごじゅう)
- 招来の不確実な大きい利益より、わずかでも今確実に手にする方が良い
お前百までわしゃ九十九まで(おまえひゃくまでわしゃくじゅうくまで)
- 夫婦が仲睦まじく、ともに長生きすることを願う言葉
「共に白髪の生えるまで」と続きます。
こちらを略して「共白髪」と言いますよね。
可愛さ余って憎さ百倍(かわいさあまってにくさひゃくばい)
- ある人に感じていた愛情が、何かをきっかけに憎しみに変わると、愛情の分だけに組む気持ちが強くなるということ
ここで会ったが百年目(ここであったがひゃくねんめ)
- 長い間、探していた相手に巡り合った時に、逃さないという決意を表す言葉
「百年」というのは、決着の付く時を意味しています。
酒は百薬の長(さけはひゃくやくのちょう)
- 酒は適量であれば、どんな良薬よりも健康によいものだ
雀百まで踊り忘れず(すずめひゃくまでおどりわすれず)
- 雀は死ぬまで飛び跳ねる鳥だということから、幼い時に身に付けた習慣は年をとってからは改まらないというたとえ
いろはかるた(京都)の1枚。
道楽癖が治らないということに使われていました。
読書百遍義自ずから見る(どくしょひゃっぺんぎおのずからあらわる)
- どんな難しい書物でも、何度も繰り返して読めば、意味や内容が自然と分かってくるものだ
「三国志・魏氏」が出典です。

百害あって一利なし(ひゃくがいあっていちりなし)
- 弊害ばかりを生み出して、利益になるような良いことは何一つ無いこと
百年河清を俟つ(ひゃくねんかせいをまつ)
- いつも濁っている黄河の水が澄むのを待つように、いくら待ち望んでも実現できないこと
「春秋左伝・襄公八年」の故事に基づきます。
単に「河清を俟つ」とも言います。
百聞は一見に如かず(ひゃくぶんはいっけんにしかず)
- 何かを理解するためには、人の話を何度も聞くよりも、一度でも自分の目で見て確かめたほうがよい
経験の大切さを説いたことわざです。
百里を行く者は九十里を半ばとす(ひゃくりをいくものはくじゅうりをなかばとす)
- 何事も完成が近づくと気がゆるみ失敗しやすいから、九分あたりでようやく半分と心得て、最後まで気を抜いてはいけない
「戦国策・秦策」が出典です。
百家争鳴(ひゃっかそうめい)
- いろいろな立場の知識人や文化人が、自由に意見を発表し論争するさま
「千」が入ったことわざ
悪事千里を走る(あくじせんりをはしる)
- 善い行いはなかなか人に知ってもらえないが、悪い行いや良くない評判はあっという間に知れ渡ってしまう
「悪事千里を行く」とも言いますが、一度落とした信用を回復するのは大変ですからね。日頃の行動から正しましょうという戒めを感じます。
値千金(あたいせんきん)
- きわめて尊い値打ちがある
海千山千(うみせんやません)
- 海に千年、山に千年住んだ蛇は龍になるという言い伝えから、経験豊かで、世の中の裏表に通じており、したたかで抜け目がないこと
親の意見と茄子の花は千に一つも無駄は無い(おやのいけんとなすびのはなはせんにひとつもむだはない)
- 無駄な花を咲かせない茄子のように、親が注意する言葉も一つとして役に立たないものはない
囁き千里(ささやきせんり)
- ささやくように話しただけでも、すぐに遠くに知れ渡るという意味で、秘密が漏れやすいことのたとえ
千載一遇(せんざいいちぐう)
- あるかないかの滅多にないぐらい良い機会
袁宏「三国名臣序賛」が出典です。
千里の堤も蟻の穴から(せんりのつつみもありのあなから)
- ごくわずかな油断や不注意から、大事が起こることのたとえ
蟻が作った小さな穴から、堤防が崩れるという意味です。

千里の道も一歩から(せんりのみちもいっぽから)
- どんなに遠大な計画も第一歩を踏み出すことから始まるものだ
千慮の一失(せんりょのいっしつ)
- どんなに賢く優れた人でも、千回に一回ぐらいは誤りもある
- 十分に考えていても、思いがけない失敗がある
「史記・淮陰侯伝」が出典です。
原文では「千慮の一得」とセットです。
千慮の一得(せんりょのいっとく)
- 愚かな人でも千回に一回ぐらいは、良い考えを思いつくものだ
「史記・淮陰侯伝」が出典です。
原文では「千慮の一失」とセットです。
鶴は千年 亀は万年(つるはせんねん かめはまんねん)
- 鶴と亀のように、寿命が長くめでたいことを祝う言葉
「万」が入ったことわざ
風邪は万病のもと(かぜはまんびょうのもと)
- 風邪をひくと、体力が落ちて、色々な病気になってしまうから、風邪を引かないように用心しないといけない

人間万事塞翁が馬(にんげんばんじさいおうがうま)
- 人の幸不幸は、すぐに変わるので予測できないものだ
「塞翁が馬」だけでも使います。
不幸だと思っていたことが幸運をもたらし、幸運だと思っていたことが不幸をもたらすので、一喜一憂しないほうが良いといういましめもあります。
万事休す(ばんじきゅうす)
- もはや手の施しようがなく、打つ手が何もないこと
万能足りて一心足らず(ばんのうたりていっしんたらず)
- あらゆることに秀でているが、一番大事な真心が欠けている
まとめ
数字が使われていることわざは、まだまだありましたが、今回は150個に絞ってご紹介いたしました。
すでに知っていて普段使っていることわざもあれば、初めて知るものも多かったです。
個人的には、これから「正直は一生の宝」と「百里を行く者は九十里を半ばとす」をモットーにしたいと思います!
-

ことわざ一覧!有名なことわざを意味も一緒に500連発!
昔から使われてきたことわざは、それだけで意味が通じて、会話が締まるという便利なものですよね。 また、人前で話すようなときに、内容と合致したことわざを一つ入れるだけで、とても気が利いた印象を与えることも ...
-

動物が入ることわざ・慣用句一覧!130個の意味を分かりやすく一挙に!
動物や生き物が使われていることわざは多いですが、いざとなるとなかなか思い浮かばないものですよね。 犬や猫といった身近な動物は、もちろんのこと、昔の生活に欠かせなかった馬や牛などなど。 また、意外と数が ...
-
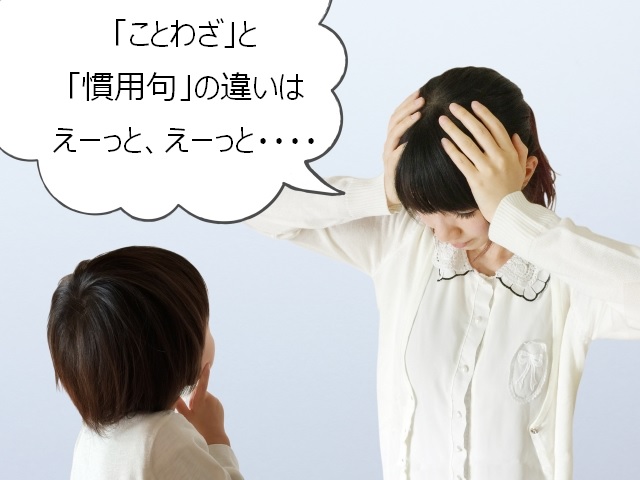
ことわざと慣用句に違いはあるの?区別が曖昧になる理由を徹底解説
ことわざを調べてみると、ことわざと思っていたものが慣用句だったり、またその逆もあったりしますよね。 しかも、見る辞書によって言っていることが違うということもままあります。 個人的には、ことわざと慣用句 ...