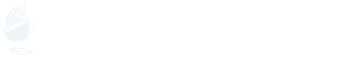会社の式典などの最後に、一本締めが入ることがありますよね。
一本締めも学生時代にはなかなか経験することが少ないですから、社会に出て初めてという人も多いのではないでしょうか。
私もそうした一人でしたが、最近、一本締めと言われたときに手を打つ回数が1回なのか10回なのか、よく分からなくなってきました。
”確か10回だよね?” と思っていたら1回だったり、”そうか、1回なんだ” と思っていたら10回だったり。
そうそう一本締めの機会もないだけに、間違えると目立ちそうなのが嫌ですよね(笑)。
そこで本日は、一本締めについて、詳しくお伝えしていきますね。
正式な一本締めの手をたたく回数は?

一本締めの手を打つ回数、正解は1回ではなく10回でした。
1回だけ打つ手締めは、一丁締めというのが正式名称だったんですね~。
また10回手をたたく一本締めは、関東を中心に行われてきた江戸締め。
関東以外でも、それぞれの地域ごとに、大阪締めや名古屋締め、博多締めといった手締めがあります。
ですが、最近は、地域の特色が失われて、何でも東京スタイルが標準化してきていますよね。
手締めも例外ではなく、江戸式の一本締めもしくは一丁締めが全国的に優勢になっているようです。
話を元に戻して、どうして一丁締めが一本締めと混同されるようになったのか、その違いは何なのかを続いて見ていきたいと思います。
一丁締めは一本締めに混同されるようになったのはなぜ?

一丁締めと一本締めの関係を見ていく前に、そもそも一本締めとは何なのかからお伝えしていきますね。
一本締めは丸く納まったことを感謝する手締め
一本締めは、関東を中心に行われてきた手締めで、10回手を打つことでしたね。
実は、10回手を打つことにこそ、一本締めの意味が隠されているのです。
- 一本締めのやり方
- 「お手を拝借」
- 「いよーお!」(”祝おう”が転じた掛け声です)
- パパパン、パパパン、パパパン、パン!(3回・3回・3回・1回と手を打つ)
- 「ありがとうございました!」(拍手~)
3回手を打つことを3回繰り返すと、手を叩く回数は9回です。
9を漢字にすると、「九」ですね。
最後にもう1回だけ手を打つわけですが、この1回は「九」に一画加えたとみなされて、「九」が「丸」の字に変わり、会が”丸く納まった”ことを表します。
一本締めは、式典や会合、商談が無事に終了したことを感謝するために行うものなのです。
3回の手打ちを3回、そして最後に1回という流れにこそ、一本締めの意味があることは分かりました。
では、1回だけ手を打つ一丁締めにはどういう意味があるのでしょうか。
一丁締めは一本締めのエコ版?
残念というか何というか、一丁締めは、単に短気な江戸っ子気質が生み出した略式の手締めでした。
最初の9回を省略して、最後の”パン”だけで、”丸く納まった”と代用しちゃったわけです。
手締めをすると、景気のいい雰囲気になりますし、今よりも、一本締めをする回数が多かったのかもしれませんね。
10回手を打つよりも、”パン”と1回だけの方が、威勢もよく、締まる感じも好まれたのでしょう。
格式の高い場や正式な集まりは一本締め、それ以外の軽い打ち上げなどは一丁締めと使い分けされるようになりました。
- 一丁締めのやり方
- 「お手を拝借」
- 「いよーお!」(”祝おう”が転じた掛け声です)
- パン!(1回だけ手を打つ)
- 「ありがとうございました!」(拍手はしない!)

一本締めと一丁締めのやり方で気をつけないといけないのが、最後の拍手です。
一本締めは拍手ありですが、一丁締めでは拍手をしてはいけません。
その理由は、拍手で、1回締めた会が開くことになるためとのこと。(一本締めは開かないのが不思議ですが・・・)
なーんか、一本締めしますよーと言われて一丁締めをしていたときを思い出すと、拍手していたような記憶があります。
周りもパチパチ拍手していましたから、こうしたしきたり事って難しいなぁと改めて思いました。
一丁締めが一本締めに混同されるようになった原因はプロ野球?
一本締めも一丁締めも関東で行われていた手締めでしたが、略式の一丁締めの方が、する機会も場も多かったのは想像に難くありません。
そこから、一丁締めには、関東一本締めなんていう俗称がついてしまい、これまた混同に拍車をかけることにもなったのです。
さらに、一丁締めと一本締めの混同を全国区にしたのは、プロ野球のキャンプ。
キャンプの打ち上げで行われる一丁締めをテレビ局が「一本締めでキャンプを締めくくりました」と放送してしまったのですね。

テレビ局が間違えたら、そりゃ広まりますよねぇ。
ですが、一丁締めと一本締めは、そもそも違うものということが分かってスッキリしました(笑)。
番外編!その他の手締めをご紹介!
番外編として、関東以外の地域の代表的な手締めをいくつかご紹介していきますね。
大阪締め
その名のとおり、大阪を中心に行われてきた手締めです。
- 大阪締めのやり方
- 「打ちまーしょ」 ⇒ パンパン
- 「もひとつせー」 ⇒ パンパン
- 「いおうて三度」 ⇒ パパンパン
- 「おめでとうございます」(拍手~)
博多締め
福岡市の博多で行われてきた「博多手一本」と呼ばれる手締めです。
- 博多締めのやり方
- 「よー」 ⇒ パンパン
- 「まひとつしょ」 ⇒ パンパン
- 「いおうて三度」 ⇒ パンパンパン
博多締めも一丁締めと同じく、最後に拍手してはいけないそうですよ。
-

「宴もたけなわ」ってどういう意味?由緒正しい言葉と分かって驚くよ
飲み会や宴会を締める言葉といえば、「宴もたけなわではございますが」。 学生のコンパや飲み会では、ほぼ登場しませんが、会社の飲み会では判を押したように毎度出てきます(笑)。 そういうもんだと思っていれば ...
まとめ
会社の式典などで、参加者全員で一本締めをして会を締めくくることがあります。
一本締めで会を締めますと言われたときに、手を打つ回数が1回だったり10回だったりすることがありますが、正しくは
- 手を10回打つ方が、一本締め
- 手を1回打つ方は、一丁締め
です。
全国各地に独自の手締めがあり、一本締め・一丁締めは関東を中心に行われてきた手締めです。
一本締めは、「いよーお」の掛け声の後に、パパパンと手を3回打つことを3回繰り返し、最後にパンと1回と叩くという流れが、「九」に一画足して ”会が「丸」く納まり参加者に感謝する”ことを表すものです。
そして、短気な江戸っ子が、一本締めから最後の1回の手打ちだけを取り出し簡略化した手締めが一丁締めなのです。
略式の一丁締めの方が、する機会も場も多かったであろうことから、一本締めと混同されるようになっていきます。
さらに、プロ野球のキャンプの打ち上げで行われていた一丁締めを「一本締めでキャンプを締めくくりました」とテレビ局が放送したため、全国的に混同されるようになりました。
これから式典などで手締めを担当する機会がある方は、「手を1回だけ打ちます」とか、「パパン、パパン、パパン、パンの方です」とか、言ってもらえると、間違えることもなくて有難いですね!