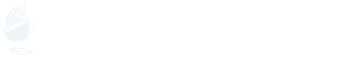6月といえば、皆さんは何を連想されますか?
私にとっては、6月はたった一言、『梅雨!』なのですが、それだとあんまりですよね(笑)。
あ、それと梅雨の他にもう一つありました。6月は早くも1年の半分が終わる月でした!特に前の会社が、6月が中間決算だったので、上期の目標期限という大きな大きな区切りの月でした。
このように、6月と聞いて思い浮かべる事柄や、6月ならではの気候などがありますよね。思い浮かべることは、人それぞれ違う事もありますし、やっぱり多くの人と共通している事もあります。
そこで本日は、「6月といえば」から連想する事柄や行事・記念日などを総まとめでお届けします!
6月といえば○○!

詳しい説明は後にゆずるとして、まずは“6月といえば○○”に入る言葉や事柄をずらーと上げたいとおもいます。
なお、単に紹介しても面白くないので、過去5年に新聞各紙に掲載された回数が多い順にランキング形式でご紹介しますね。(え?それも大して面白くない?)
| 順位 | 6月から連想する○○ | 掲載回数 |
| 1位 | 梅雨 | 40,618 |
| 2位 | 父の日 | 5,982 |
| 3位 | 夏のボーナス | 3,589 |
| 4位 | 衣替え | 3,167 |
| 5位 | 山開き | 2,949 |
日経テレコン過去5年間(2013/3/13~2018/3/12)に掲載の全国80紙の記事から検索
*衣替えは3/14~6/13の3ヶ月を集計
やはり1位は梅雨でしたね!まぁ、梅雨には、梅雨入り、梅雨前線と関連する言葉も多いので回数が増えてしまうという側面もありますが、、、
6月の前の月である5月は、ゴールデンウィークもあったりで、母の日は5位に終わったのですが、父の日は2位と上位にランクインしましたね
6月は祝日がないことが父の日的には幸いしている?と失礼なことを思いつつ、この後に続けて6月についての基礎知識や行事や記念日などを詳しくお伝えしていきますね。
6月とはこんな月です
今でこそ、月は1月から順番に12月まで数字がついていますが、昔は月ごとに呼び名がありました。
梅雨で水の多い時期なのに、“無い”と違和感がありますが、この“無”は“~の”という意味をもつ連体助詞なのです。つまり、水無月は「水の月」ということですね。
ただ、ここでいう水は雨のことではなく、田植が終わった田んぼに張られる水のこと。人々にとって、農作業が大きな関心事だったことが分かりますね。
それでは、次は6月の暦について見ていきましょう。
6月の暦(こよみ)と祝日
暦と書くと、日づけ・カレンダーというよりも、今も生活の中に根付いている区切りという印象がありませんか?同じく、生活に直接関わってくる祝日と合わせてお伝えしてきますね。
入梅(つゆいり)
気象庁が発表する梅雨入りではなく、6月11日ごろは暦の上で決められた入梅(つゆいり)です。
これも昔は稲や作物を育てるうえで、梅雨にいつ入るのかは、とても重要なことでした。今のように天気予報もない時代です。6月11日頃には梅雨に入ると決めて、農作業の予定を立てる目安にしていました。
気象的にも、本州・四国・九州は毎年6月中旬ごろに梅雨入りを迎えます。オホーツク高気圧と小笠原高気圧の間に発生する梅雨前線が7月中旬の梅雨明けまで停滞します。
驚いたことに、梅雨前線は日本の本州から中国の揚子江流域にまでかかる長さがあるのです。6月という月は、東アジア一帯が梅雨ですね。
夏至
6月21日ごろは、夏至の日です。1年中で最も昼の時間が長くなる日ですね。この日を境に、冬至に向けて徐々に昼の時間が短くなっていきます。
強い陽射しに空気が温められて、暑さのピークは2ヶ月遅れの8月にやってきます。
夏越の大祓
1年の半分がちょうど終わる6月30日は、各地の神社で「夏越の大祓(なごしのおおはらえ)」があります。大きな茅の輪が鳥居の近くに置かれるのも夏越の祓ならでわ。
夏越の大祓では、茅の輪をくぐって、1年の前半の穢れや厄災を祓い、残りの半年の健康と無事を祈ります。
また、京都には、6月30日に食べる「水無月」という和菓子を食べる風習があります。この前後には、京都の和菓子屋さんでは必ずありますので、ぜひ一度召し上がってみてください。
-

水無月ってどんな和菓子?由来とあわせて徹底的にご紹介!
6月になると、京都の和菓子屋さんには必ず並ぶ「水無月(みなづき)」という和菓子があります。 京都では、小さなおまんじゅう屋さんでも売られていますし、本当に身近なお菓子です。 それなのに、大阪の友人に「 ...
祝日
6月は、1年の中で、唯一、祝日のない月です。
2016年に最も新しい祝日の山の日が出来ましたが、“8月11日という夏休み期間に祝日って要る?”と多くの人が感じたのではないでしょうか。
山の日も当初は、6月が有力候補だったそうですが、ゆとり教育による学力低下が心配されたことから8月になったと言われています。
有給の消化率が低い日本では、祝日でも作らないと労働時間が減らせませんが、祝日を増やすことで、これ以上学校の授業時間も減らせないという苦肉の策というところでしょうか。
“何だかなー”な話ですが、気を取り直して6月の行事を見ていきたいと思います!
6月の行事
父の日
6月の第3日曜日は、父の日ですが、デパートに行っても、母の日とは比べると、売り場全体ひっそりしているのは気のせいでしょうか(笑)。
そんなちょっと地味目な父の日ですが、始まりは母の日と同じく20世紀初めのアメリカです。
1909年、アメリカのワシントン州でソノラ・スマート・ドッドという女性が、母親が早くに亡くなったため男手一つで6人の子供を育てた父を讃えて、父の誕生月である6月に教会で礼拝をしたことがきっかけです。
その少し前の1908年に母の日が始まっていました。ドッドさんは、同じように父に感謝する父の日を作ってほしいと牧師協会に訴えて、1910年に初めての父の日の式典が開かれました。
ドッドさんが父親の墓前に白いバラを供えたことから、父の日の花はバラの花です。母の日のカーネーションとは違って、世のお父さん方はバラを貰ってもオロオロしそうですね。

夏のボーナス
個人的にはボーナスは6月より7月ですが、公務員の夏のボーナス支給日が6月30日のため6月といえば○○の中にボーナスが入ってきます。
一般企業のボーナス支給日は7月上旬というところがほとんど。
いずれにしても、6月30日を皮切りにボーナスの支給時期が始まります。
衣替え
6月1日は、学校やオフィスの制服が夏服に変わる衣替えの日です。
平安時代の宮中では、中国の風習に習って、旧暦の4月1日に夏服に、10月1日には冬服に着替える「更衣(こうい)」という行事が行われていました。
6月1日の衣替えは、この「更衣」から生まれた習慣です。ちょっと前は肌寒くても、一斉に半袖になりましたが、最近は、柔軟に対応する学校や企業が増えてきましたね。

山開き
6月は、各地の山で登山シーズンの始まりを告げる山開きが行われます。
今でこそ、登山はレクリエーションやスポーツとして親しまれていますが、かつて、登山は宗教的な行事として行われていました。
そのころには、普段は神聖な山に登ることが禁止されており、夏の一定期間だけ山に登ることが許されていました。登山解禁の日に、山の神様をまつって、登山の安全を祈るために行われていたのが、山開きの儀式です。
ジューンブライド
結婚を司る女神Juno(ギリシャ神話ではヘラ)が6月を守護していることから6月のことを英語ではJuneと言います。
そのため、欧米では、6月に結婚するジューンブライドは、女神の加護を受けて、幸せになると言われています。
日本にジューンブライドが紹介されたのは1967年ごろ。梅雨の時期は婚礼も少ないことから、ホテルやブライダル業界が何とか6月の婚礼を増やそうとした作戦の一つです。
とはいえ、やはり6月は雨も多く高温多湿。ジューンブライドは浸透しましたが、6月の婚礼数は今も多くは無いようです。

6月の記念日
続いては、6月の記念日を集めれるだけ集めてみました。では、一気にご覧ください!
| 日にち | 記念日 | 由来 |
| 6月1日 | 電波の日 | 1950年6月1日に電波三法*が施行されたことを記念して、1951年に総務省が制定しました。*電波法、放送法、電波監理委員会設置法 |
| 6月第1日曜 | プロポーズの日 | ブライダルファッションデザイナーの桂由美さんが、ジューンブライドにちなんで定めました。 |
| 6月2日 | 横浜港、長崎港開港記念日 | 1859年に日米修好通商条約が締結され、下田港・函館港に加えて横浜港と長崎港が開港しました。 |
| 6月5日 | 環境の日 | 1972年6月5日にストックホルムで国連人間環境会議が開かれたことを記念し、1993年に環境基本法で、この日を環境の日に定めました。国連でも、この日を「世界環境デー」と定めています。 |
| 6月6日 | 楽器の日 | 歌舞伎や能など、伝統芸能の世界では6歳になる6月6日に稽古を始めると上達すると言われていることにちなんで、1970年に一般社団法人全国楽器協会が定めました。 |
| 6月9日 | 我が家のカギを見直すロックの日 | 2001年に、「6.9(ロック)」の語呂合わせから日本ロックセキュリティ協同組合が定めました。この日には、防犯意識の向上を呼び掛けたイベントが全国で開かれます。 |
| 6月10日 | 時の記念日 | 1920年に東京天文台(現・国立天文台)と財団法人生活改善同盟会が、「時間をきちんと守り、欧米並みに生活の改善・合理化を図る」ことを目的に制定しました。 |
| 6月14日 | 世界献血デー | 2005年に世界保健総会会議で記念日として承認されました。 |
| 6月16日 | 和菓子の日 | 明治時代まで、6月16日は嘉祥の日として和菓子を食べて厄除けと健康を記念する風習がありました。1979年に全国和菓子協会が、嘉祥の日の復活と和菓子の素晴らしさを伝えるために制定しました。 |
| 6月18日 | ホタテの日 | 「ホ」を分解すると「十八」になることと、6月がホタテの旬の時期であること、陸奥湾の「むつ」も語呂が合うことから、6月18日をホタテの日として青森県漁業協同組合連合会とむつ湾協業振興会が定めました。現在では、毎月18日をホタテの日としています。 |
| 6月21日 | スナックの日 | かつて夏至の日には、粽に似た「カクショ」というお菓子や、お正月のおもちを固くして食べる「歯固め」という週間があったことから、全国菓子協会がこの日をスナックの日と定めました。 |
| 6月22日 | ボウリングの日 | 1861年6月22日に長崎県で発行された英字新聞にボウリング場開店の告知が掲載されました。日本初のボウリング場であるとして、1972年に社団法人ボウリング協会が定めました。 |
| 6月26日 | 露天風呂の日 | 岡山県の湯原温泉が「町づくり事業」の一環として、1987年に「6・26(ろ・てん・ぶろ)」の語呂から、定めました。 |
| 6月28日 | 貿易記念日 | 1859年6月28日、それまでの鎖国政策を転換し、アメリカ・イギリス・フランス・オランダ・ロシアの5か国に対して、横浜・長崎・函館の3港を開き、貿易を許可すると公布した日です。 |
| 6月29日 | 佃煮の日 | 1646年6月29日に佃煮と関連の深い東京の佃島に住吉神社が造営されました。このことから2004年に全国調理食品工業協同組合が佃煮の日に定めました。 |
6月は幕末の開国に関連した記念日が多い月でしたね。
では、最後に各地で開かれる主なお祭りとイベントを見ていきましょう。
各地で開かれるお祭り・イベント

梅雨の時期ではありますが、6月も各地でお祭りやイベントが開催されます。北海道から順番に主なお祭り・イベントをご紹介しますね。
北海道
- さっぽろライラックまつり
- YOSAKOIソーラン祭り
5月下旬から6月初旬にかけて、大通り公園や川下公園周辺で開催される。音楽会や写生会、スタンプラリーや、野菜の直売所・野外喫茶コーナーなどが楽しめる。
6月初旬の水曜日から日曜日まで、5日間にわたって開催される。
大通り公園や札幌駅前など、市内のあちこちの会場で、地元札幌はもちろんのこと、県外や海外からの参加チームが演舞を披露し競い合う。
期間中は200万人を超す見物客を訪れる一大イベント。
東北
- チャグチャグ馬コ
6月の第2土曜日に岩手県の滝沢市と盛岡市で行われる国の無形文化財に指定されているお祭り。
華やかに飾り付けられた100頭余りの馬が、滝沢市の鬼越蒼前神社から盛岡市の盛岡八幡宮までを行進する。
祭の名前、チャグチャグは、馬につけられる鈴の音から付けられた。

関東
- 横浜開港祭
- 山王祭
6月2日の開港記念日の前後に「Thanks to the Port(開港を祝い、港に感謝しよう)」と開かれるイベント。
みなとみらいの臨港パークをメイン会場として、パレードや世界各国の食べ物を集めたフードコートなどがあり、音楽と光の花火ショーがフィナーレを飾る。
2年に一度(偶数年)の6月の上旬から中旬にかけて行われる東京・日枝神社の祭礼。
江戸時代には、祭礼行列が江戸城に入り、将軍が見学したことから「天下祭」と呼ばれた。江戸三大祭りの一つ。
近畿
- 夏至祭
- 姫路ゆかたまつり
三重県伊勢市の二見興玉(ふたみおきたま)神社で夏至の日に行われる神事。
夏至の日は、夫婦岩の間から太陽が昇るため、早朝の海に入り禊を行いつつ日の出を待つというもの。
6月22~24日に行われる兵庫県姫路市にある長壁神社の祭礼。祭礼用の衣装を持たない町民のために、浴衣着用を許可したことから、ゆかた祭りとなった。祭で立ち並ぶ露店の数が西日本最大規模であることでも有名。
- とうかさん大祭
6月の第一金曜日から日曜日にかけて行われる広島県広島市にある圓隆寺の稲荷大明神の大祭。
伝統のあるお祭りで2019年が400年記念に当たる。広島市では、このお祭りで浴衣を着るのが、その年の浴衣の着始め。
九州
- 鹿島ガタリンピック
佐賀県鹿島市で5月下旬から6月上旬ごろに開催されるイベント。
有明海の干潟を利用した色々な競技が企画される。事前に申し込めば誰でも参加できるものの、近年は人気が高く抽選になっている。泥んこになるのを楽しむ珍しいイベント。

6月も北海道から九州まで、ユニークなイベントがありますね!最後のガタリンピックは、怖いもの見たさで参加してみたい気が(少し)します(笑)。
まとめ
5月といえば、多くの人が連想するのは、梅雨入り(入梅)、ちょうど半年、父の日など。
新聞で過去5年に取り上げられた中では、梅雨が、一番件数が多いという結果でした。次いで父の日、夏のボーナス、衣替え、山開きと続きます。
また6月21日ごろは、昼の時間が最も長くなる夏至を迎えます。12の月の中で唯一祝日が無い月というのも6月の特徴です。
本州から九州地方は6月中旬ごろに梅雨入りし、気温も湿度も高い日が続きます。夏に向けて暑さに体を慣らしていく時期ですね。
-

7月といえば何?連想する言葉から行事・記念日まで総まとめ!
7月といえば、皆さんは何を連想されますか? 京都在住の私にとっては、7月といえば祇園祭の月です。 会社が鉾を出す町内にあったので、粽売りのお手伝いをしたのもいい思い出です。 こんな風に7月から必ず思い ...